こんにちは 公認心理師のヒロです。
ふだんは子育て支援分野で
お子さん・親ごさん・先生などを中心に
心理師として応援しています。

怒りたくないのに怒ってしまう

子どもがなかなかいうことを聞いてくれない…
こどもと関わる大人がしばしば抱える悩みです。
とても辛いですよね。
そんな、子どもとの関りについての悩みに対処するとき
役に立つ考え方があります。
それが

ポジティブ行動支援(PBS)
です。
今回はポジティブ行動支援をご紹介し
子どもとのかかわり方の基本的なコンセプトをお知らせします。
これを知っていただくことで
子どもと良いかかわりをすることの良さを
改めて見直すことができると思います。

もうできてるよ
と思う方でも新しい発見があるかも。
子どもたちの未来をもっと明るく!ポジティブ行動支援とは
先ほど ポジティブ行動支援(PBS) と言う言葉を紹介しました。
ポジティブ行動支援とは
子どもたちの問題行動をただ抑え込むのではなく
「なぜその行動をするのか?」という原因を探り
子どもがより良い生活を送れるように支援する考え方 です。

例えば、
- 「何が学校に行きたくない気持ちにさせるの?」と子どもの気持ちを聴く
- 「〇〇ができるようになったね!」と子どもの良いところをたくさん褒める
- 「もしなんの障害もなかったら本当はどうしたい?」と希望を聞く
このように
子どもの気持ちを聞き
「今できる行動」に目を向けて
できることを増やしせるよう応援する
このような関りをすることです。

PBSが生まれた背景
PBSは、1980年代にアメリカで重度の障害を持つ人々が
より人間らしい生活を送る権利を求める声が高まったことから生まれました。
それまでは、問題行動に対して罰を与えたり
隔離したりといった方法が一般的でしたが
このような方法は人の尊厳を傷つけるだけでなく
問題行動を根本的に解決しない ことがわかってきたのです。

そこで、
という視点から、PBSが生まれました。

日本でも、「ほめましょう」というアドバイスが
昔と比べるとだいぶ増えてきましたが
このような影響を受けているのではないでしょうか。
近年は特に、教育分野でこのような関りが
大変注目されてきています。

社会的な潮流の高まり→ 哲学(ノーマライゼーション、インクルージョン、本人中心の価値観)の体系化 → 行動分析学を土台にPBSが誕生
・1950年代にバンク・ミケルセンによって提唱され、米国においてはウェルフェンスバーガーによって理論化された「ノーマライゼーション」の思想
※ 障害を持つ人と持たない人が平等に生活する社会への実現
・米国のアフリカ系アメリカ人や他の少数民族の機会均等などを求める「公民権運動(civil rights movement)」により人種、宗教、民族、出自、信条に基づく差別が禁止され、障害者に対する差別禁止やサービス拡張についての議論その後「脱施設化運動」が起こり、施設入所者の減少、障害者の生活水準の向上、人権擁護が社会的に求められるようになりました。
「それは甘やかしではないでしょうか」という大人の誤認
このようにポジティブな行動に焦点をあてる支援に対して

ほめると調子に乗る

甘やかしだ

大人になったら。ほめられることばかりではない
などと反発されることもありますが
これは、短期的で、大人の目線でしか
こどもを見ていないと思います。
たしかに子どもが怖がるような対応をすれば
すぐに言うことを聞いてくれます。
しかし、子どもは怒られることに慣れていきますし
怒る人のことを嫌いになり
怒られることにも慣れていきます。
したがって時間とともに悪いことが
積み重なるサイクルに入っていくのです。

それに罰的対応をすると、生涯にわたって子どもの心身に
大きなダメージを残すことがわかっています。
大人から見て小さな罰だったとしても
それが積み重なることによって
やがて心疾患に繋がっていくのです。

それでは先のように子どもを褒めることに
抵抗を示す大人は、本当に怒りたいのでしょうか?
私はそうは思いません。
本当は子どもに、正しいこととまちがいを区別できるようになってもらい
自分で判断し、ちゃんとした大人になってもらいたいのだと思います。

それならば、まちがいに対しては小さく指摘(注目)し
正しい方法に強く注目することによって
より正しい方法をとれるように気持ちを
高めて上げられれば、子どものまちがいを減らすことができるのです。

PBSの3つのポイント
- 予防が大切;問題行動が起こってから対応するのではなく、事前に問題行動が起こりにくい環境を作ることが大切です。
- 子どもの良い行動を褒める;子どもが何か良い行動をした時は、具体的に褒めてあげましょう。
- チームで取り組む;保護者だけでなく、学校、地域の皆さんなど、みんなで子どもをサポートすることが大切です。

PBSを始めるにあたって
PBSを始めるにあたって、大切なことは「子どもを理解すること」です。
子どもがどんなことに興味を持っているのか
どんなことで悩んでいるのか、など
まず子どもを知ることが、効果的な支援につながります。

PBSが提唱された初期は障害のある人を対象とした個別的な対応の研究が中心でした。Kincaid (2018)によると、PBSの研究は以下のような流れで変遷しているようです。
近年減少した研究は
- 自閉症スペクトラム障害のある者を対象とした研究
- 家庭場面や施設場面で実施された研究
- 家族によって実施された研究
- データに基づくアセスメント手続きが用いられた研究
逆に増加した研究は
- 群間比較デザインが用いられた研究
- 行動面に関する困難性のリスクを持つ参加者を対象とした研究
- 障害のない成人を対象とした研究
- 通常教育場面において実施された研究
- 臨床の専門家によって実施された研究
- 介入整合性や社会的妥当性に取り組んだ研究
- SWPBIS(学校全体で積極的な介入と支援を行い児童生徒の問題行動を予防する)
このような流れから、最近では障がいのない人への適用へと発展しました。
事例:Aくんの場合
Aくんは、学校で友達と上手く遊べずに、いつも一人ぼっちでした。
そのため、学校に行くのが嫌になり、不登校になってしまいました。

そこで、保護者は家のA君の様子を観察するようにしました。
学校に行かないことで、保護者は悩んでいましたが
A君とよく会話をし、一日の過ごし方を決め
しなければならないこと、守らねばならないこと
最低限必要な勉強などをすることにしました。
そうしているうちにAくんは
絵を描くことにはまっていきました。

そこで学校に急に行かせるのではなく
放課後登校から少しずつ慣らして行き
図画工作から教室に入ってみる作戦を練りました。
学校ではAくんが好きなテーマの絵を描けるようにしたり
他の生徒にもAくんの絵を見せたりする機会を作りました。

また、保護者も、家でAくんと一緒に絵を描いたり
絵画教室に通わせたりするなど
Aくんの才能を伸ばせるように支援しました。
その結果、Aくんは、学校で認められることが増え
自信を持つことができるようになりました。

そして、少しずつ友達と話すことができるようになり
学校にも少しずつ行けるようになったそうです。
まとめ
PBSはこんな風に広がっています。
PBSは、子どもたちの問題行動をただ抑え込むのではなく
子どもがより良い生活を送れるように支援する考え方です。
PBSは、当初は障害のある子どもたちへの支援として注目されていましたが
近年では、発達障害のある子どもや、不登校の子どもなど
様々な子どもたちへの支援として活用されるようになってきました。
また、学校だけでなく、家庭や地域社会でも実践されるようになっています。
より良い未来のために
PBSは、子どもたちの未来をもっと明るくするための、一つの考え方です。
この考え方を参考に、お子さんと一緒に
より良い未来に向かって進んでいきましょう。
もし、お子さんが不登校でお悩みでしたら、
一度、PBSについて調べてみてはいかがでしょうか。
またお子さんにとって何が良いのかご一緒に考えませんか?
もし、この記事を読んでお子さんのことで何か相談したいことがあれば
お気軽にご連絡ください。
ご相談はこちらから
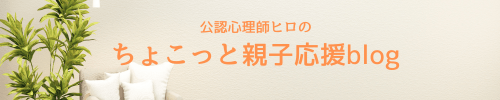


Comments